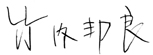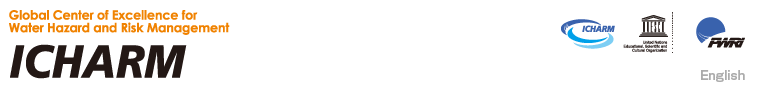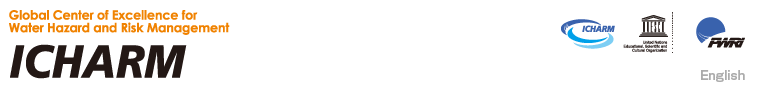1. 竹内センター長からのメッセージ
まずは、7月中葉の、西ジャワ島津波の犠牲者、また中国、ベトナム、フィリピン、韓国一帯から、日本の中部・西日本に広がる豪雨災害の犠牲者に、深く哀悼の意を表します。特にPangandaran,
West Javaの津波については、予警報システムの整備が遅れていたことが原因の一つであり、 ICHARMもその進捗に向け、働きかけの一端を担いたいと思っております。
ICHARMは本年3月6日発足以来、本格活動に向けて、意欲的な取り組みを開始しました。ハザードマップ研修、予警報システムの研究開発など、既定の活動の他、新しい計画、協力体制の強化の面でも、大きなステップを踏み出しました。中でも国交省を中心に、各方面の方々にご参加いただいて、協力体制を組んでいただきましたことは、今後の国内支援体制の強化に向け、大変意義深いことと思います。
5月10日には、国連大学に国内の関係者をお招きして、発足記念シンポジウム「世界の水災害軽減に向けて」を行いました。国際活動に関心のある方々を中心に、 80名ほどにご参加いただき、ICHARMの目標、基本方針について、さまざまなご意見をいただきました。
それに先立つ4月27日には、河川局の中に国際戦略検討会を発足いただき、河川局全体の統合的国際戦略の一環にICHARMを位置づけ、総合的効果を挙げるための、検討を始めていただきました。またこれと並行して、4月5日、5月23日、6月22日、7月26日と月一のペースで、国際実務経験者を中心にした勉強会を開いていただいています。いずれも熱意渦巻く会合で、ICHARMはその期待に応えるべく、毎回沢山の宿題に取り組んでいます。
7月3-7日にパリのユネスコ本部で、第17回IHP(国際水文学計画)政府間理事会が開かれ、 ICHARMからも、私と寺川グループ長が出席しました。 ICHARMは、前期2年間のIHP活動の目玉の一つとして、各種報告で繰り返し言及され、協力の申し出も相次いで、大きな注目を集めました。特にEU(欧州連合)のFlood
Directive、中国揚子江委員会、インド国立水文研究所、米陸軍工兵隊水資源研究所からの協力提案は、大きな展開に発展することが期待されます。米陸軍工兵隊水資源研究所とは、初日午前の審議直後、本会議場で各国代表が見守る中、ピエトロフスキー所長と私により、包括的な研究協力についての覚書(MOU)の署名式が行われました。
今理事会では、ICHARMの諮問委員会委員6名が、各地域より選出され、坂本理事長指名の委員とあわせ、 13名が確定しました。各委員には、9月15日の諮問委員会でのご助言を始め、ICHARMの世界的役割遂行に向け、強力なご指導をお願いいたします。
政府間理事会に先立つ6月30日、7月2日の二日間、同ユネスコ本部で、 IAHS・ユネスコ共催のKovacs Colloquium(コバッチ会議)「洪水研究のフロンティア」が開かれ、
ICHARMも活動方針の紹介をしました。 Call for an Alliance for Localismと題して、災害の危機に直面する現地の人々の、問題の実態に正面から取り組みたいと、Localism(現地主義)の抱負を述べました。このLocalismは、上に述べましたいくつもの意見交換会を通じ、皆さんの共通の認識として沸きあがってきた方針です。「水災害は原因も結果も、国や地域によりまったく異なっているので、その多様性を正しく認識し、真に現地住民のニーズに応えられる活動をする」と言うものです。普遍的技術や制度の普及さえできれば問題は解決すると言うような、安易な発想を戒め、現地住民の身になって考えることを、ICHARMの看板にしたいと思います。今後9月15日の諮問委員会に向けた、ICHARM活動の骨太計画も、Localismを中心に立案したいと思っています。
この5ヶ月の間に、国際公募のスタッフが2名加わり、国際スタッフは計4名になり、陣容も充実してきました。さらに6名の国際公募の準備をしております。
9月14日国連大学において、ICHARM発足記念国際シンポジウム「Alliance for Localism」を開催します。これへのご参加をはじめ、ますますのご協力を、お願い申し上げます。
水災害・リスクマネジメント国際センター
センター長 竹内邦良