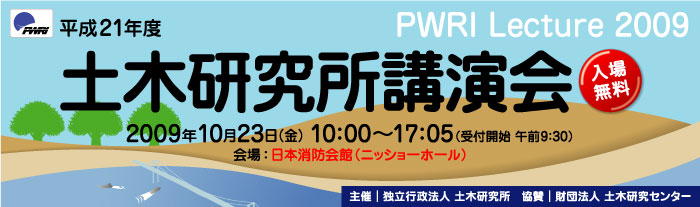平成21年2月に山形県鶴岡市七五三掛(しめかけ)地区の民家およびその周辺に亀裂が生じた。その後も亀裂が拡大するとともに新たな亀裂も多数発生し、長さ約700m、幅約400mの地すべりが原因であることが明らかになってきた。住民は避難生活を余儀なくされ、この地すべり災害はテレビでも報道された。地下水排除等の緊急対策により地すべりは7月中に沈静化したものの、この間の地すべりの移動量は6mに及んだ。この地すべりの変状の進行と応急緊急対策により地すべりが沈静化するまでの経過について報告する。
平成21年7月中国・九州北部豪雨において、中国地方、九州北部に多くの土砂災害が発生した。特に、7月21日の豪雨により、山口県防府市を中心に100件以上の土砂災害が発生し、14名が死亡した。土木研究所土砂管理研究グループ火山・土石流チームでは、7月22〜29日まで国土交通省中国地方整備局および山口県の要請により、現地調査及び技術支援を行った。そこで、ここでは災害の状況・調査結果について報告する。
グラウンドアンカー(以下、アンカー)が我が国に導入され50年近く経過している。導入初期には施工や防食の技術が開発途上であり、アンカーの機能の消失によるのり面の変状、腐食による部材の破断などの問題も見られる。このような背景のもと、土木研究所は(社)日本アンカー協会と、アンカーの健全性診断と補修技術に関する共同研究を実施し、その成果をもとに既設アンカーの維持管理手法を示す「グラウンドアンカー維持管理マニュアル」(鹿島出版会)を2008年7月に発刊した。本講演では同マニュアルの概要について説明を行う。
地震や豪雨によって発生した斜面崩壊土砂が谷を埋塞し、天然ダムを形成する災害が近年注目されている。特に2004年の新潟県中越地震、昨年の岩手・宮城内陸地震によって発生した天然ダムは社会的にも大きな影響を与えた。これに対して土砂管理研究グループでは、天然ダム形成後に直ちに実施する監視業務のために「天然ダム監視技術マニュアル(案)」を取りまとめた。ここでは、実際の対応事例を含め監視技術を分かりやすく説明する。
河川を生態系にとって良い環境にするには、本来河川や河岸が有している機能や働きを再生・保全することが重要である。河岸処理では護岸を設置せずに洪水に対して許容できるかどうかの判断を行い、護岸を設置する場合にも計画・設計では生息のための空隙・のり勾配に配慮する。また、水際域では生態系に配慮した“入り組み、植生のカバー、照度”に関する工夫が必要であり、以上について事例を含めて発表する。
我が国には、環境基準を超過する濃度の自然由来の重金属を溶出あるいは含有する岩石・土壌が普遍的に分布している。自然由来の重金属による影響は、土壌汚染対策法で扱う人為由来の重金属の土壌・地下水汚染とは性質が異なるため、土壌汚染対策法等で定められる方法では適切に評価・対応できない場合が多く、現場で問題となっていた。本講演では、自然由来の重金属等に対する適切な対応方法に関する土木研究所の取り組みと成果について紹介する。
下水処理プロセスの中で、水と分離された液状汚泥の濃縮はその後の処理効率を左右する重要な工程である。土木研究所では、簡易な装置でこの効率を向上させる「みずみち棒」を開発し、2008年には、その計画から管理までの考え方を整理した技術資料を策定した。本講演では、経験の少ない技術者にもなじみやすいQ&A形式の技術資料集の内容とともに、現場と一体となったユニークな策定プロセスについて紹介する。
土木研究所では、社会のニーズに適った利用価値の高い知的財産を戦略的に創造し、適切に保護し、積極的に活用していくため、この度「知的財産ポリシー」を制定した。本講演では、その概要を紹介するとともに、成果普及において重要な役割を担う知的財産権の保護・活用の状況等について述べる。また、重点的に普及を進めている主な技術や普及活動の概要等を紹介するとともに、普及の結果としてどの程度の経済効果等を社会に還元しているかについて述べる。
| 山口県柳井市生まれ、昭和49年柳井高校卒業 昭和53年お茶の水女子大学 理学部数学科卒業 |
|
| 慶應義塾大学 理工学部 教授、 NPO法人建築技術支援協会常務理事 建設トップランナーフォーラム顧問、 内閣府 規制改革会議委員 農水省・経産省 農商工連携88選審査委員長、 林野庁 山村再生プラン選考委員 日本プロジェクト産業協議会 森林再生事業化研究会主査 等 |
|
| 建設産業、建設産業の新分野進出(農林業含む)、 地方活性化、 森林再生 規制改革に関わる研究・支援活動 |
|
| 『建設業 残された選択肢―ホンモノの経営してますか』(同友館) 平成19年 『日本には建設業が必要です』(建通新聞社) 平成17年 『建設帰農のすすめ』(中央公論新社) 平成16年 『田中角栄と国土建設-列島改造論を越えて』(中央公論新社) 平成15年 『建設業の新分野進出─挑戦する50社』(東洋経済新報 社) 平成15年 『建設業 再生へのシナリオ』(彰国社) 平成12年 |
今後急速に高齢化が進む社会資本を適切に管理していくためには、点検、評価、予測、補修・補強といった技術や全体としてのシステムが不可欠となる。土木研究所では道路橋に関するこれら技術について研究開発を行うと共に、その成果が管理の実務で活用されるよう要領やマニュアル類としてとりまとめ、公開している。今回の講演会ではその全体像について紹介すると共に、代表的なマニュアル類について土研の研究成果もふくめ、ポイントを解説する。
老朽化したトンネルの増加に伴い、ひび割れなどの変状が覆工に発生しているトンネルが増えてきている。限られた予算の中で変状が発生したトンネルの維持管理を効率的に行うには、変状の早期発見と変状状態に応じた適切な対策の実施が重要となる。本講演では、トンネルの変状状態から変状の発生原因を推定し、発生原因に応じた適切な対策工を選定する方法に関する土木研究所での取り組みとその成果について紹介する。