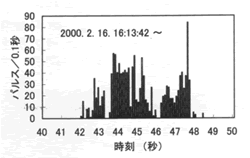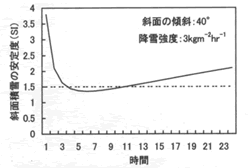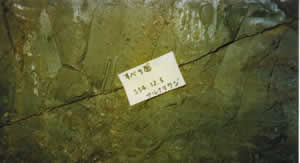| 新潟試験所ニュース |
| 妙高・幕の沢における雪崩発生と気象・積雪観測
1. はじめに 表層雪崩の発生を予測するためには、雪崩が発生する条件を知る必要があり、そのためには雪崩の発生事例と発生に至るまでの気象や積雪データを蓄積することが必要である。しかしながら、一般に雪崩が発生する山岳地域では気象や積雪観測が困難であり、詳細なデータはなかなか手に入らない。また、人里離れたところでは雪崩の発生時刻を知ることも容易ではない。そこで、2000年2~4月、雪崩が頻発する妙高山麓の幕の沢末端付近(標高約820m)に雪崩発生検知システム(飯倉他、2000)を設置して雪崩発生時刻と規模を自動的に記録するとともに、近くで連続的に気象観測をし、1週間毎に積雪断面観測を行った。観測の詳細は新潟試験所ニュース(2000.8月号)を参照されたい。 2.雪崩の発生
消雪後に 回収した検 知システム のデータを 図-1に示し た。これは、 雪崩の衝突 によって生 じた震動が パルス数と して記録さ
れたもので、この記録から2月16日16時13分に雪崩が発生したことがわかった。このシステムは雪崩の規模を4段階で判断でき、記録された雪崩の規模は最大級のレベル4であっ
た。この他に雪崩の記録はなかった。 3.気象・積雪観測結果 図-2に2月の24時間 降雪深と日最高気温を 示した。14 日に低気圧 が日本付近 を通過、日中の気温が 2.2℃まで上昇した後、強い冬型の気圧配置となり寒気が入った。関山における15日~16日にかけての24時間降雪深は88㎝で、今冬期最高であった。 |
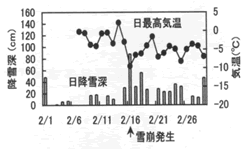 |
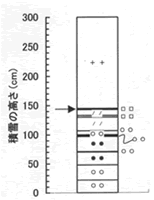 |
| 図-2 24時間降雪深と日最高気温 |
図-3 2/18の積雪層構造 |
|
4.斜面積雪の安定度
新潟県などの本州の豪雪地帯では気温が氷点下で大雪が降った場合、顕著な弱層がなくても降雪中やその直後に表層雪崩が発生することが多いといわれている(Endo,1992:遠藤、1993:
納口、1992)。2月16日に幕の沢で起きた雪崩も大雪の最中に発生した。そこで、不安定な新雪の崩壊によってこの雪崩が発生した可能性について考察した。 5.集水管内酸素濃度低下方法の現地試験 本観測から以下のことがわかった。 |
| (文責:竹内) |
|
(リングせん断試験機)
地すべり斜面には、移動する土塊と移動しない土塊との間に写真-1に示すすべり面があり、このすべり面には極薄い(数mmの場合もある)粘土(すべり面粘土)が存在しています。また、地すべりは、重力による土塊の滑動力が、その力に抵抗するすべり面粘土のせん断強さより大きくなった時に発生します。したがって、地すべりの発生を防止するためには、常にすべり面のせん断強さを滑動力より大きくしておく必要があり、そのために地すべり防止工事が行われています。 |

|
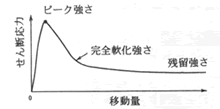
|
| 図-1 すべり面のせん断強さ | |
 |
|
| 写真-2 リングせん断試験機 | 図-2 リングせん断試験の供試体 |