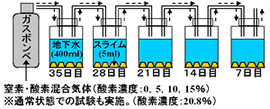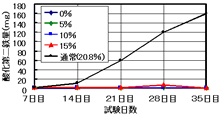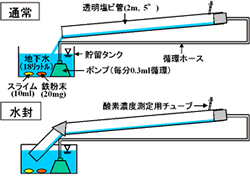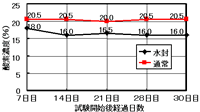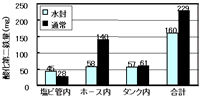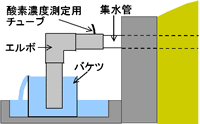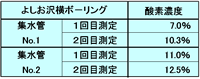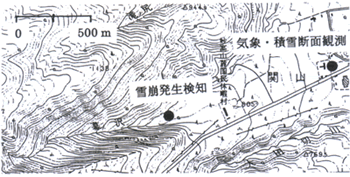| 新潟試験所ニュース |
| 地下水排除施設の機能低下に関する試験調査
1. はじめに
地下水排除施設(横ボーリング,集水井)は、地すべり斜面内に集水管を挿入し、地すべり発生誘因である地下水を排除することで斜面の安定を図るものです。しかし、施工後の時間経過に伴い、地下水排除量が減少するといった機能低下現象を示す例が多く、斜面の不安定化が懸念されています。 2.集水管内スライム付着防止のための追加試験 新潟試験所ニュ−ス第2,8,10号で紹介した調査・試験では、下記の結果が確認されました。 2.1 ガラスビン内スライム生成試験
ガラスビン内において、鉄細菌によるスライム生成量が酸素濃度を低下させることによりどのように変化するか試験しました。
図−2は、試験開始後の経過日数とガラスビン内に付着した酸化第二鉄量との関係を示したものであります。酸素濃度 が通常状態では、経日変化により酸化第二鉄量の増加が認められるのに対し、酸素濃度15%以下では、酸化第二鉄の生成がほとんど無い状態となっております。このことより、酸素濃度低下に伴いスライム生成が抑制されたことを確認できました。 |
|
2.2 横ボ−リング模型内スライム生成試験
横ボ−リング模型内において、外気からの酸素流入を遮断したものと、遮断してないものにおいて、スライム生成量がどのように変化するか試験しました。
図−4は、水封処理有無別の試験開始後経過日数と試験装置内の酸素濃度との関係を示したものであります。水封を行った装置は、水封を行っていない装置に比べ、酸素濃度が低い状態を示しております。
図−5は、水封処理有無別の試験装置内酸化第二鉄生成量を示したものであります。水封を行った装置は、水封を行っていない装置に比べ、酸化第二鉄生成量が少ない値を示しております。 (3)集水管内酸素濃度低下方法の現地試験
現地試験は、実際の地下水排除施設(横ボーリング)において、2本の集水管を対象に実施しました。この試験の目的は、図−6に示した。
表−1は酸素濃度測定結果を示したものであります。集水管内の酸素濃度は7〜13%を示し、水封処理を行うことで大きな酸素濃度低下を図れることが確認されました。このことより、集水管孔口の水封処理によってスライム生成を抑制できる可能性のあることが分かりました。今後は、更に現地試験を継続していき、直接スライム付着抑制効果について確認していく予定であります。 |
| (文責:安藤) |
|
雪崩は、重力による駆動力が、積雪層を支持する力を上回るときに起こると考えられていますが、特に大きな被害をもたらす表層雪崩は、全層雪崩に比べて発生場所や時期の予測が困難であるため、雪崩対策上の問題になっています。そこで、気象・積雪データから積雪強度を推定し、雪崩発生の予測手法を確立することを目指した研究を行
っています。 |

|
表 観測項目
|
||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||
| 写真−1 雪崩発生検知システム | 写真−2 気象観測システム |