 |
| 1.展示ブースの様子 |
 |
| 2.護岸付近で採捕した昆虫を展示しました |
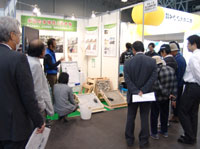 |
| 3.デモンストレーションの様子 |
 |
| 4.サワガニの登坂の様子 |
 |
| 5.子ども達は生きている昆虫に興味津々です |
 |
6.スタッフが説明している様子
 |
| 7.COP10会議関係者も来場されました |
|
|
愛知県名古屋市にあるポートメッセなごやにおいて、「環境・エネルギー」をテーマにメッセナゴヤ2010が開催されました。自然共生研究センターでは、「水辺の多様性と生き物」をキーワードに出展を行いました。
メッセナゴヤは、「愛・地球博」の理念を継承する事業として、2006年からスタートした国際総合見本市で、企業や団体の業種・規模を問わず各々の誇る技術や製品、サービスを情報発信する場所です。第5回目を迎える今回は、生物多様性条約第10 回締約国会議(COP10)連携事業でもあり、期間中多くの来場者が訪れました。
出展では、河岸や水際部が本来有する環境上の機能(生物の生育・生息空間や移動経路)についての研究に関する「護岸に集まる昆虫類」の展示と「生物の登坂実験」のデモンストレーションを行いました。
「護岸に集まる昆虫類」の展示では、現在当センターの実験河川で行われている、護岸の環境の違い(湿潤度や温度変動)によって集まる昆虫類を調べる調査や、昆虫類の好む環境条件を調べる研究について紹介するために、実際に今回の展示用として捕まえた昆虫(クモ、アリ、コオロギ、ダンゴムシなど)やその写真、標本も展示しました。それらは顕微鏡や虫めがねを使って、来場者に見たり触れたり自由に扱ってもらいました。
「生物の登坂実験」のデモンストレーションでは、昨年当センターで行われた、陸と水中を行き来する生物にとってどんな斜面が登りやすいのかを調べた研究で実際に使用された、表面の凹凸が異なる5種類のパネルを使いました。具体的な方法はパネルの交換に加えて、斜面の角度を4段階(約26.6度、約33.7度、45度、約63.4度)変えて、生物が登坂できるかです。昨年の研究では、ヌマガエル・クサガメ・サワガニを使用しましたが、今回の展示会ではクサガメとサワガニを用いました。
登坂実験のデモンストレーションは、1日2回程行われ、毎回来場者の多くが立ち止まって見学をされました。特に週末には、子ども達が登坂実験のデモンストレーションや展示の昆虫に興味津々の様子でした。また、今回はCOP10連携事業として、関係者に特別公開される場があり、外国人の来場者も見学に訪れました。
展示や実験に興味を持った方々の中には、実験に使用したパネルや生物について質問されたり、コンクリートの護岸でもほんの少し凹凸があれば、生物にとって行き来しやすい環境になることに、大変感心している様子でした。また、以前当センターが行った水際の機能に関する研究や、実河川での自然再生の取り組みの事例について興味深く耳を傾けていました。
(小椋 祥子)
|