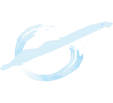サイトマップ
トップページ
センター紹介
研究成果
- ARRCNEWSより
- 官民連携の川づくり・河川管理を目指して
- ダム下流の生物に配慮した適切な土砂供給を目指して
- 中小河川の課題を理解し、現場で使える技術を開発する
- 大河川に特徴的な氾濫原環境の保全を目指して
- ダム下流に土砂を流す
- 中小河川の維持管理を巡って
- 守るべき河岸の環境機能
- 二枚貝の減少と再生への道
- 河岸・水際域を保全・修復するために
- 流量、土砂、生物相を回復させ、健全な河川生態系を取り戻す
- 危急生物イシガイ類の生息環境はどうして劣化するのか?
- 河川環境を理解する上で捉えにくい要因を分析する
- 水草の機能を活かす
- 石の隙間を利用する魚たち
- 川の流れと付着藻類
- 川の一次生産と自濁作用
- 水生生物にとっての水際域の機能
- 河川の流量管理
- 寄生虫から川の生態系を見る
- 実験河川における研究解説パネルの開発
- 河原植物と外来植物
- 魚の生息場所と生息量の関係
- 活動レポートより
平成28年度研究成果
- 二枚貝の生息に適したワンド・たまりの冠水条件は河川によって異なりますか?
- 礫洲への種子の定着量に影響を及ぼす要因は何でしょうか?
- 河川景観に馴染みやすい護岸ブロックのテクスチャーの評価方法はありますか?
- ダム下流に土砂を含む放流が行われた場合、付着藻類はどのように変化するでしょうか?
- ダムからの土砂供給によって、魚類の餌内容は変化しますか?
平成27年度研究成果
- 高水敷掘削後に形成されるワンド・たまりの数と二枚貝の生息量は経年的に変化しますか?
- 治水・環境・維持管理計画のサポートするための具体的な指標ツールはありますか?
- 大型コンクリートブロックにおける景観上の配慮のポイントは何ですか?
- 河床に細粒土砂が堆積して石礫が埋没すると、アユにどのような影響がありますか?
- 淵に土砂が堆積し水深が減少するとどのような魚類に影響しそうですか?
- ダム下流の河床材料の変化が魚類に及ぼす影響を評価する方法はありますか?
- 河床に砂を供給した後、付着藻類の現存量はどのように変化しますか?
平成26年度研究成果
- 二枚貝の生息に適した「たまり」の幅を教えてください。
- 河川環境を定量的に評価するツールはありますか?
- 環境が劣化した中小河川で瀬・淵を創出するにはどうすればよいですか?
- 河川景観保全のために必要な緑化ブロックの植被率について教えて下さい。
- 川が濁るとアユはどのような行動をとるのでしょうか。
- ダム下流の河床材料の変化が魚類に及ぼす影響を評価する方法はありますか?
- 研究に関する情報の展示には、どのようなメディアが適しているのでしょうか。
平成25年度研究成果
- 二枚貝が好む「たまり」の形状や特徴とは?
- 川幅の変化は何に影響を与えますか?
- 護岸の景観パターンを選ぶ際の留意点を教えて下さい。
- 付着藻類にたまったシルトは、どのくらいの時間で洗い流されるのでしょうか?
- 川底の凹凸が変化すると遊泳魚も影響されるのですか?
- 「生物多様性」の展示では、どのような話題が扱われているのでしょうか?
平成24年度研究成果
- 河川下流部で優先的に保全・再生を図るべき場所を見つける方法はありますか?
- 濁った水の中での魚の行動はどのように把握できるでしょうか?
- 帯工や落差工よりも水生生物の移動や生息に配慮した工法はありませんか?
- 中小河川の河床地形は何によって決まりますか?
- シルトを多く含んだ藻類を水生昆虫は食べるのでしょうか?
- 河川生物の生態は、どうすれば効果的に伝えることができるのでしょうか?
- 護岸に使用されるコンクリートブロックの表面形状は河川景観に影響しますか?
平成23年度研究成果
- 濁水に含まれる成分によって、礫表面の付着藻類への影響は異なるのでしょうか?
- 川底をたくさんの砂が覆うと底生魚はどうなりますか?
- 二枚貝がたくさん棲める場所には、魚類もたくさん棲めるのでしょうか?
- 高水敷をどの高さで切り下げれば二枚貝の生息可能な水域ができるでしょう?
- 維持管理が容易となる中小河川の工夫を教えてください。
- 川の形を測る最新の方法にはどのようなものがあるのですか?
- 護岸表面のテクスチャーは、どのように評価すればよいのでしょうか?
平成22年度研究成果
- 天然記念物イタセンパラが生息する水域の特徴は?
- 護岸はどのような色や形状であれば、周囲の景観と調和するでしょうか?
- 護岸のり面の湿潤度や温度変動の違いは、非飛翔性生物の多様性に影響するでしょうか?
- 魚が水際部にできる流れの遅い場所を必要とするのは、どんな時でしょうか?
- 濁水が付着藻類に及ぼす影響は、流速によって異なるのでしょうか?
- 1年を通して魚が棲める水路の条件とは?
- 人工水草を入れると池の透明度が向上するのですか?
平成21年度研究成果
- 天然記念物ミヤコタナゴの浮上稚魚はどんな場所にみられるでしょうか?
- 河岸を利用する生物にとって、どのような河岸法面が登坂しやすいでしょうか?
- 土砂還元は河川の一次生産をどのように変化させるのでしょうか?
- ワンドの冠水頻度や底質の違いは、水生生物の定着に影響するでしょうか?
- どうして冠水しやすいワンドでは、魚類の多様性が高いのでしょうか?
- タナゴ類が棲める水路はどのような環境でしょうか?
- 河川環境の基礎知識をフィールドで学ぶことはできますか?
平成20年度研究成果
- ワンドの造成は水生生物に良い効果をもたらすのでしょうか?
- 水際域を修復するための効果的な木杭群の配置パターンは?
- 川の水が増えたとき、遊泳魚は石の隙間に避難するのでしょうか?
- 自然河岸と護岸された河岸では、河岸の構造や機能はどのように異なるのでしょうか?
- アユやオイカワによる摂食によって、河床付着膜の性状は変化するのでしょうか?
- 土砂還元の効果を客観的に示す方法はないのでしょうか?
- どうして洪水の影響を受けるワンドが淡水二枚貝の生息に適しているのでしょうか?
- 体験学習を通じて得た部分的な情報を、有機的に結びつける方法はありますか?
平成19年度研究成果
- 魚種によって石の隙間の好みは異なるのでしょうか?
- 水温の下がる冬、魚類はどんな場所で越冬しているのでしょうか?
- 木杭群の配置パターンが異なると魚類生息量に違いが見られるでしょうか?
- アユの摂餌は、河床付着膜にどのような役割を果たしているのでしょうか?
- 土砂還元を行うと、河床の生物相は変わるでしょうか?
- どのような“ワンド”や“たまり”が希少性二枚貝の生息にとって適当なのでしょうか?
- フィールドで捉えにくい自然現象を理解する方法はありますか?
平成18年度研究成果
- 石の大きさが違うと、その隙間を利用する魚類は異なるのでしょうか?
- 増水時、水際植生は魚類の定位場所として機能するのでしょうか?
- 希少性二枚貝はどのような生息環境を必要とするのでしょうか?
- アユの摂餌は、河床付着膜にどのような役割を果たしているのでしょうか?
- ダム下流では、河床の環境変化によって生物相がどう変わるのでしょうか?
- 流量改変に伴う河床環境の変化は予測できるでしょうか?
- 水面下で見えにくい魚類の生息場をわかりやすく伝える方法はありますか?
平成17年度研究成果
- 川の流量は底生藻の一次生産速度に影響を与えますか?
- 流量増加に伴う河床付着膜の剥離・掃流の程度を予測することはできるでしょうか?
- 水際タイプが異なると、魚類の生息状況に違いはあるのでしょうか?
- 天然記念物ネコギギはどんな形の川を好むのでしょうか?
- 河川環境を人に伝えるにはどんな方法が効果的でしょうか?
平成16年度研究成果
- 水際の明るさの違いにより、魚類の生息状況には変化が見られるのでしょうか?
- 自然河岸と護岸では、水際の構造や機能はどのように異なるのでしょうか?
- 夜行性の希少魚であるネコギギは昼間、どんな場所にいるのでしょうか?
- 流量の違いによって川の生産と呼吸に変化は見られるでしょうか?
- 人は、川底の「きれいさ」をどのように評価しているでしょうか?
- 出水時、魚類はどのような行動をとっているのですか?
- 流量と生物の関係を、体験を通じて学ぶには、どのような方法があるでしょうか?
平成15年度研究成果
- 実験河川の上流・中流・下流区間では生産・呼吸速度は異なるのでしょうか?
- アユの餌としての付着膜の維持にも川底の攪乱は必要なのでしょうか?
- 水際植物は水中部と水上部に分かれます。水上の植物は魚にとって必要でしょうか?
- 代替工作物で水際植物の機能は再現できるでしょうか?
- コイ科魚類の子供達の恒常的な成育場所はどのような場所でしょうか?
- 河川流量の増減は魚類にどのような変化をもたらすでしょうか?
- 植物の種子は水中でどのような挙動を示すでしょうか?
平成14年度研究成果
- 洪水時に流れる物質は平常時と比較してどのように違うのでしょうか?
- 付着性藻類の流れやすさは、種によって異なるのでしょうか?
- 植物で覆われた川岸がコンクリート護岸に変わると、水生生物はどのように反応する
でしょうか? - フィールドで観察しにくい川の現象をわかりやすく伝えるにはどのような方法が考え
られるでしょうか?
平成13年度研究成果
- 河岸の植物は、川底にどのような影響を及ぼすのでしょうか?
- 実験河川の生態系は、周囲の河川と比べてどのような特色があるのでしょうか?
- 河原の砂の中にはどのような植物の種子が、どのくらい入っているのでしょうか?
- 季節によって、魚類のすみかはどのように変わるのでしょうか?
平成12年度研究成果
- 単調な環境の河川で復元工法を実施すると、魚類の生息状況はどのように変化する
でしょうか? - 洪水が起きた時、増えた水は川のどの部分にどれくらい貯められるのでしょうか?
- 外来植物の繁茂は河原の在来植物にどのような影響を与えるのでしょうか?
- 川の中のとらえにくい事象をわかりやすく伝えるためには?
平成11年度研究成果
- 研究論文等の一覧
- 研究コラム
技術相談
イベント
-
平成28年度イベント
-
平成27年度イベント
-
平成26年度イベント
-
平成25年度イベント
-
平成24年度イベント
-
平成23年度イベント
-
平成22年度イベント
- 第1回「流域からの流出土砂が河川に及ぼす影響」セミナーを開催しました
- メッセナゴヤ2010に出展しました
- 岐阜県自然共生工法研究会による「実験河川見学会」を開催しました
- 長期宿泊体験学習 ~淡水魚類調査交流活動~
- 中学生が実験河川で調査を体験しました
- 実験河川にて「川歩き」「生き物さがし」を実施しました
- 実験河川で「生き物探し」を行いました
- 実験河川で「外来種・流れる水のはたらき」について学習しました
- 川の楽校2010 ~川にすむ生きものの目~ を開催しました
- 実験河川で「川の構造」について学び「生き物探し」を行いました
- 実験河川のフィールドを活用して河川環境研修を実施しました
- 親子参加による「川は友だち・エコツアー」を開催しました
- 「第30回全国豊かな海づくり大会~ぎふ長良川大会~」に出展しました
-
平成21年度イベント
- メッセナゴヤ2009に出展しました
- 応用生態工学会第13回埼玉大会に参加しました
- 実験河川で「流れる水のはたらき・外来種」についての課外学習を実施しました
- 実験河川のフィールドを活用して河川環境研修を実施しました
- 第550回 建設技術講習会の一環として実験河川見学会が行われました
- 河川環境楽園 川の楽校2009~発見♪探検♪川歩き~
- アクア・トトぎふ合同イベント探検!川の中~川と生き物の秘密を探ろう~
- テレビ朝日「報道ステーション」でセンターの研究内容が紹介されました
- 岐阜県自然共生工法研究会が実験河川を見学しました
- 携帯電話のQRコードを活用した実験河川の見学会を開催しました
- 全国豊かな海づくり大会プレイベント 「関市ふれあい交流行事」に出展しました
-
平成20年度イベント
- 自然共生研究センター10周年記念 研究報告会を開催しました
- 実験河川で「流れる水のはたらき」を題材にした課外学習を実施しました
- 環境フェアせき2008に出展しました
- 「水になって旅をしよう」を開催しました
- 実験河川で「川にすむ生物を観察しよう」を開催しました
- 自然共生研究センター10周年記念施設見学会を開催しました
- 実験河川で「流れる水のはたらき」を題材にした課外学習を実施しました
- 体験作文スペシャル ~ワンド探検隊~ を開催しました
- ICHEのエクスカーションで当センターの実験河川を見学して頂きました
- 米国ミネソタ大学土木工学科 Miki Hondzo教授をお招きして講演会を開催しました
- 2008夏休み親子教室「のぞいてみよう川の中」~ワンド探検隊~を開催しました
- 河川環境楽園 夏休みツアー「川の楽校」~川と水辺の生きもの~「実験河川ウォークラリー」を開催しました
- 岐阜エコプロジェクト、川は友だち・エコツアー「実験河川ウォークラリー」を開催しました
- 「ワンド探検隊 -貝と魚のふしぎな関係-」を開催しました
- 「空中写真で比べよう!昔の田んぼと今の田んぼ/小学校の周りにある水辺と生き物について学習しよう!」を開催しました
- 「パックテストと水生昆虫とで考える川の環境」を開催しました
- iPodを使ったガイドウォーク体験会を開催しました
-
平成19年度イベント
- テレビ朝日「素敵な宇宙船地球号」で,センターの取り組みが紹介されました
- 建設技術フェア2007in中部に出展しました
- 環境フェアせき2007に出展しました
- SPP事業で各務原高校生が木曽川のワンド調査を行ないました
- 応用生態工学会第11回大会に参加しました
- 公開実験-石礫吊り上げによる魚類捕獲実験-を行いました
- 河川環境研修を開催しました
- 2007年度親子教室―のぞいてみよう川の中―を開催しました
- 川の楽校「実験河川ウォークラリー」を開催しました
- 「実験河川ウォークラリー」を開催しました
- 「NPO法人長良川環境レンジャー協会主催 封入標本作成講座」を開催しました
- 多自然川づくり講習会に参加しました
- 空中写真で比べてみよう!お爺ちゃんお婆ちゃんの田んぼと 僕たち私たちの田んぼ」を開催しました
- 岐阜県関市でタナゴの放流会を開催しました
-
平成18年度イベント
- 土居氏の講演会がありました
- 「環境教育指導者のための封入標本作成講座」を開催しました
- ICLEEに参加しました
- 河川環境メッセ2006in岐阜に出展しました
- イベント「川を改造しよう」を開催しました
- 「ボトルアクアリウム -ミニ地球で生態系を学ぼう-」を開催しました
- 第3回湧くわく水サミットに出展しました
- イベント「ペットボトル箱メガネで川底観察」を開催しました
- 夏休み親子教室「のぞいて見よう!川の中 」を開催しました
- 講演会「琵琶湖周辺における水田利用魚類の季節変化とその現状」がありました
- 応用生態工学会第10回記念大会に参加しました
- 河川環境研修を開催しました
- 建設技術フェア2006in中部に出展しました
- 岐阜県関市で二枚貝の保全活動を行いました
- 環境フェアせき2006に出展しました
- 自然共生研究センター研究報告会2006を開催しました
- 公開実験「水際間隙の水中観察実験」が開催されました
- 第54回 日本生態学会 松山大会に参加しました
-
平成17年度イベント
-
平成16年度イベント
-
平成15年度イベント
- 2003 河川環境メッセin岐阜に出展しました
- 夏休み親子教室「流れをとめて水のない川を調べよう」を開催しました
- CONET2003(機械関連展示会)に出展しました
- 全国魚道実践研究会議に出展しました
- 建設技術フェア2003 in 中部 環境学習エリア
-
平成14年度イベント