|
�� �w�i�ƖړI
�@��N���{�����I��������A�I�Ԃ̌��ԁi�ȉ��A�Ԍ��j�������ꏊ�Ƃ��ċ@�\���I�a�ɂ���ċ��ނ̐������قȂ邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B�������A1�j�d�C�V���b�J�[��p������N�x�̎����ł͐����̂̑������Ԍ��ɓ������ݍ̕ߗ����Ⴂ�A2�j�����̋G�ߕω���c�����Ă��Ȃ��A���Ƃɖ�肪����܂����B�����ŁA���N�x�͊Ԍ��ɐ�������̐���S�ʔc�����A���̋G�ߕω��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ď������s���܂����B
�� �Ԍ������̕��@
�@�Ԍ��ɐ�������̂�S�ʍ̕߂��邽�߂Ɉȉ��̎菇�Ŏ������s���܂����B�@����ɂč��Ő��I��A������i�ȉ��A���I�Q�j�A�A�����͐�̐��ۂɉ������͏��ɋ��ލ̕ߗp�̖ԁi3.0m�~2.6m�j��~�݂���A�B�~�݂����ԏ�ɐ��I�Q���d�@���g���Ē݂�~�낵������i2.0m�~1.6m�j��ݒu����A�C���ނ��蒅����ڈ��ƂȂ�3�T�Ԃ��̏�Ԃ��ێ�����A�D���ޒ��������{����B�D�ł́A���I�Q�̉��ɕ~�݂����ԂŐ��I�Q���͂����ނ������ł��Ȃ���ԂƂ�����A�d�@�Ő��I�Q��݂�グ�āA���I���̋��ނ�S�ĖԂō̕߂��܂����i�ʐ^1�j�B
�@�����ɗp�����I�a��3��ށi��100�A200�A350mm�j�A�I�a���ꂼ��ɂ��Ď������3�݂��A�����ʂ̕��ϒl�Ƃ���𖾂炩�ɂ��܂����B
�� ���ʂƍl�@
�@1�j���Ғʂ���I�Q���̋��ނ�S�ʍ̕߂��邱�Ƃ��ł��܂����B���̌��ʁA�I�a���̕ω��Ƃ��ĉċG�ɂ��I�a���傫���Ȃ�ƗV�j����������X��������܂����i�}1�j�B2�j�G�ߖ��̕ω��ł́A�āA�H�A�~�ŁA���ꂼ��58m2������150�`300�̂̋��ނ��m�F����A�ċG�A�H�G�����~�G�ɂ����鐶���̐����������Ƃ��m�F����܂����i�}2�j�B���ɁA�V�j���i�^�����R�A�I�C�J���A���c�S�j�͓~�G�Ɍ̐��̑������m�F����܂����B
�@�ߋ��Ɏ��{�������ېA���Ɋւ��钲�����ʂ�����ƁA�A���тł̋��ނ̐����ʂ͏H�G�ɑ����~�G�Ɍ�������X�����F�߂��܂������A�Ԍ��ł͋t�̌X���������A�����͐�̂悤�Ȑ���ł��Ԍ��͉z�~��Ƃ��ċ@�\���邱�Ƃ��킩��܂����B����A����ꂽ���ʂ��H�@�J������̓I�Ȑ��ۈ�̕ۑS�E�C����@�Ɍ��ѕt���Ă������Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B
�S���F��X�@�O���A����@�u�N�A����@�S�� |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
 |
| ���ʐ^-�P�@�[��́g���I�Q�h |
|
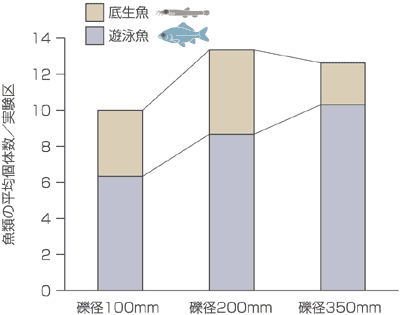 |
| ���}-1�@�ċG�ɂ������I�a���̋��ނ̕��ό̐� |
�@�@�@�@ |
|
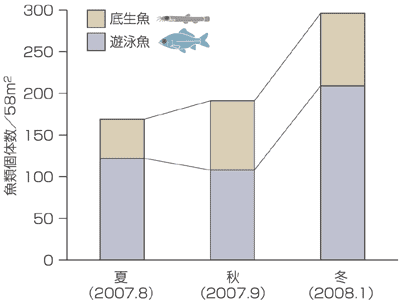 |
| ���}-�Q�@���������ʂ̋��ތ̐� |
�@�@�@�@ |
|