|
● 背景と目的
これまで、河川をテーマとした体験型プログラムは、市民や子どもたちを対象に実施した取り組みが数多く報告されていますが、河川の実務者や専門家を対象にした事例はほとんどありません。そこで、当センターでは、実験河川を活用したフィールド体験型プログラムを開発し、実践およびその評価を行いました。
● プログラムの内容
プログラム1:瀬・淵構造の形態的な特徴の理解
物理環境調査を計画・実施する上での考え方を通じて、瀬・淵構造の形態的な特徴を理解するプログラムを提案しました。ここでは、実験河川の早瀬と淵に横断測線を設定し、流速と水深、河床材料を調べました。
プログラム2:河床環境と底生動物の生息の関係の理解
底生動物は生活型と摂食機能群に分類することで、河川の環境変化のサインを読み取る指標種として用いることができます。そこで、実験河川の早瀬や淵、内岸側の砂泥に生息する底生動物を採集し、河床環境との関係を理解するプログラムを実施しました(写真1
参照)。
プログラム3:水際植物と魚類の生息の関係の理解
河川を横断方向に見た場合、水際域は多くの生物の生息場として利用されています。そこで、実験河川の植生区とコンクリート区で、電気ショッカーを用いた魚類採捕を実施し、魚種の群集構造を比較しました(写真2
参照)。
● 結果と考察
実践は平成21年8月と9月に河川の実務者30名を対象に行い、アンケート調査を実施しました。図1はプログラム1の調査結果です。受講者の82%は初めての経験でした。実践前は54%がプログラムの必要性をあまり感じていませんでしたが、実践後は73%が肯定的な意見でした。その理由を見ると、「自然界では(瀬淵の構造が)分かりにくいが、実験河川では簡単に瀬淵の形を実感することができたので良かった[30代・男性]」との回答が得られました。物理環境の各項目を実際に測定することで、早瀬と淵が持つ特徴を体験を通じて理解することができたと考えられます。フィールド体験は、河川の形態的な特徴を物理環境項目の具体的な数値に置き換えたことで、受講者は生息場を見出す新たな視点を持てたこと、フィールド体験と関連性の高い情報は効果的に習得できることが示唆されました。今後の課題としては、物理環境の調査では測定に影響が及ばない様に人数や実施場所を検討すること、体験と講義とを合わせて実施し体系化を図ることが必要です。
担当:真田 誠至 |
 |
 |
| ■写真1 プログラム2の実践風景 |
■写真2 プログラム3の実践風景 |
|
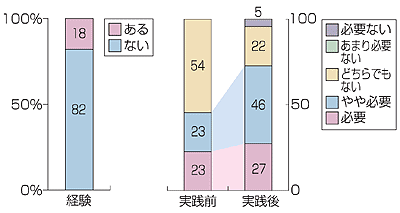 |
| ■図1 プログラム1の調査結果 |
|
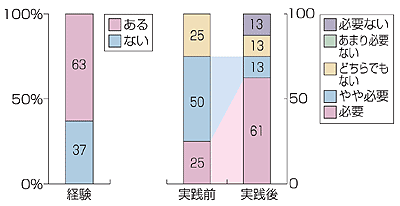 |
| ■図2 プログラム2の調査結果 |
|
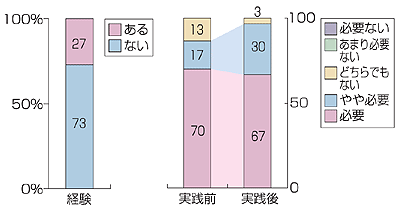 |
| ■図3 プログラム3の調査結果 |
|
|