|
● 背景と目的
氾濫原のワンドは、魚類などの水生生物の生息場、増水時の避難場として有効とされています。近年では、河川改修工事などによる河道の直線化により自然河川のワンドは減少しており、人工ワンド造成による水生生物の生息場所創出の取り組みが行われています。しかし、人工ワンドへの生物定着過程とそれに寄与する要因に関する研究は、自然河川での環境変動の要因が多岐にわたるため少ないのが現状です。そこで実験河川を使って冠水頻度とワンドの底質を操作した実験を行いました。
● 実験の方法
実験河川の氾濫原ゾーンの高水敷を冠水頻度に差をつけるために、右岸を左岸よりも20cm低くしました。そして底質の面積被覆度が明確に異なる二種類(礫質100%、砂質70%)のワンド(3×10m)を右岸と左岸にそれぞれ4箇所ずつ造成しました。魚類調査は、網モンドリを設置して行い、貝類調査はコドラード(1×1m)内を深さ10cmまで底質を掘り採取を行いました。各調査は平成21年6月と11月、平成22年2月に行いました。なお、ワンド造成後から調査終了までに右岸で61日、左岸で3日の冠水が確認されました。
● 結果と考察
生物調査の結果、13種452個体の魚類と4種784個体の貝類が採集されました。採集した個体数のうち、魚類ではモツゴが77.0%、貝類ではシジミ類が95.5%を占めていました。モツゴとシジミ類の出現パターンには、冠水頻度と底質の違いによって、次のような違いがありました。モツゴは、いずれの時期においても冠水頻度の高いワンドの方が生息個体数は多いことが確認されました(図1)。一方、底質の違いによる個体数は、時期によって傾向が異なり、明確な違いは見られませんでした(図2)。シジミ類については、各調査時期において冠水頻度の高いワンドで生息個体数が多いことが確認されました(図3)。またいずれの調査時においても砂質の方が礫質よりも多くの個体数が確認されました(図4)。以上の結果から、モツゴでは冠水頻度の違いが、シジミ類では冠水頻度と底質の違いが、それぞれの種の定着・生息に重要であると考えられました。今後も、ワンドの生物定着過程とそれに寄与する要因についてさらに調査を進める必要があると考えています。
担当:相川 隆生、佐川 志朗、久米 学、萱場 祐一 |
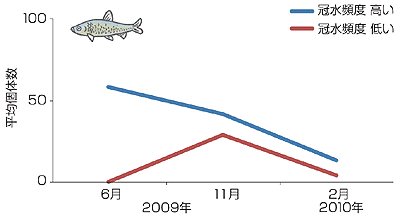 |
| ■図1 冠水頻度の違いとモツゴの平均採集個体数との関係 |
|
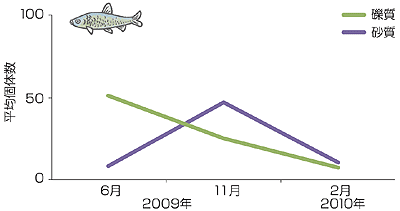 |
| ■図2 底質の違いとモツゴの平均採集個体数との関係 |
|
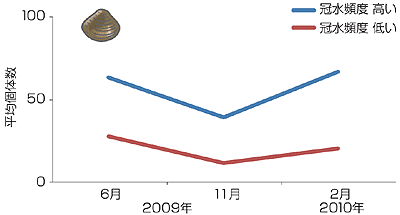 |
| ■図3 冠水頻度の違いとシジミ類の平均採集個体数との関係 |
|
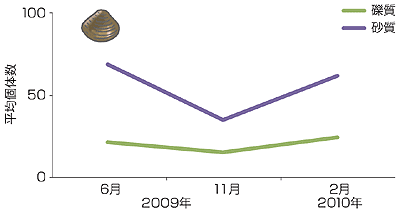 |
| ■図4 底質の違いとシジミ類の平均採集個体数との関係 |
|
|