|
● 背景と目的
貯水ダムは、砂や小礫といった通常礫間に見られる河床材料(以下、細粒河床材料)の供給量を減少させる場合があります。そのため、ダム下流において、砂などの細粒河床材料が少なくなり、大きな河床材料のみで河床が構成される「粗粒化」が発生し、河川生態系を劣化させる可能性があります。一方、ダムの上流側には下流に供給されなくなった細粒河床材料が堆積するため、これを防止する必要が生じます。「土砂還元」は、これら上流・下流での二つの相反する問題(細流河床材料堆積・粗粒化)を解決するための一つの方策であり、近年いくつかの貯水ダムで行われ始めています。しかし、土砂還元によって粗粒化がどの程度改善されるのか、また、劣化した生態系機能に対して実際に改善効果があるのかどうかなど、客観的な評価に関する知見は多くありません。そこで、土砂還元のもつ河川環境修復効果を知ることを目的とし、ダム下流において土砂還元を行っている阿木川ダム(岐阜県恵那市、木曽川水系)を対象に、ダム上流区間、ダム下流区間、ダム下流区間に合流する支川において土砂還元前後の調査を行いました。
● 結果と考察
調査の結果、土砂還元の前は、ダム下流において細粒河床材料が非常に少なく粗粒化を確認できますが(ここでは、コドラート内に占める砂の被度面積を指標とした)、土砂還元後には細粒河床材料が増加していることが分かりました(図1)。ただし、砂の占める面積はダム上流・支川等と同レベルには回復していません。次に、生態系機能の指標となる底生動物群集を見てみます。底生動物は様々な生活型に分けられ、その中には細粒河床材料を巣材や棲み場所に利用する携巣型、掘潜型と呼ばれるものがあります(図2)。図3は、これら細粒河床材料を利用する分類群の合計個体数が、底生動物全個体数の何割となっているのかを示しています。土砂還元を行ったダム下流においてのみ、有意な増加がみられ、ダムの影響を受けないダム上流・支川と同レベルにまで回復したことが分かります。
これらの結果から、土砂還元は河床粗粒化の改善・底生動物群集の群集内訳修復効果を持つことが明らかとなりました。今後は、どのような土砂還元手法が、最も効果的に環境改善・生態系修復するかを考えていく予定です。
|
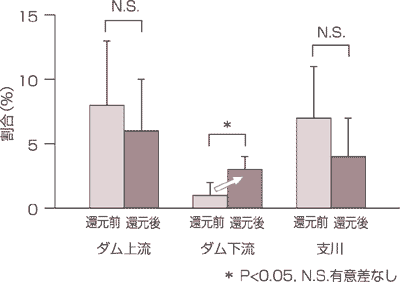 |
| ■図-1 河床材料に占める砂の割合 |
 |
|
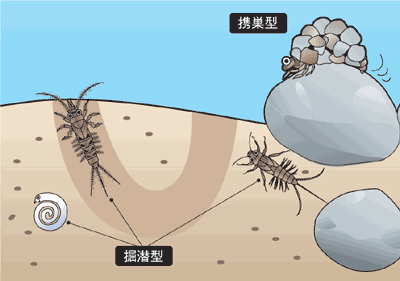 |
| ■図-2 土砂を利用する分類群 |
 |
|
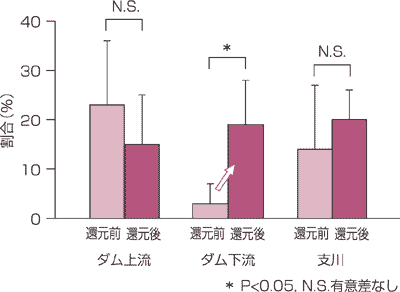 |
| ■図-3 細粒河床材料を利用する分類群の出現割合 |
 |
|