|
● 背景と目的
河川環境の保全においては、流況の改善や生物の棲み場を修復し、健全な生態系の構造や機能を回復させることが重要です。本研究は、生物による河床付着膜摂食と河床環境の関係に着目し、生物の摂食が河床付着膜の性状に果たしている役割を評価し、今後の河川環境管理に反映させることを目的としています。これまでの実験から、アユによる摂食は、シルト等の微細な土粒子の河床への堆積や大型糸状藻類の繁茂を抑制すること、景観の維持に寄与するなど、河床の健全性の維持に大きな役割を果たしていることが明らかになってきました。本年度は、雑食性のオイカワの摂食が河床付着膜の性状に及ぼす影響、及びアユ、オイカワの摂食が付着藻類の活性に及ぼす影響を評価することを目的に実験を行いました。
● 方法
実験河川に実験区(幅2.5m×長さ4m)を設け、付着物のない新たな礫(径約15cmの玉石)を河床に敷き並べ、付着膜を成長させた後、アユを放流した「アユ区」(放流密度:1個体/m2)、オイカワを放流した「オイカワ区」(放流密度:4個体/m2)、いずれも放流しない「対照区」を設定しました。その後、それぞれの河床から付着膜を採取・分析し、付着膜の性状や光合成速度(明暗瓶法による、写真1)を比較しました。
● 結果
珪藻の出現割合が大きい付着膜に対しては、アユだけでなくオイカワの摂食によっても、生藻類比(生きている藻類の割合を表す)や強熱減量(%)の増加などの質的な改善効果が認められました(表1)。
図1に各実験区の単位クロロフィルa、単位時間当たりの最大光合成速度を示しました。「アユ区」の最大光合成速度が最も大きく、次いで「オイカワ区」、「対照区」の順で、摂食された付着藻類の光合成速度は、摂食されない付着藻類よりも大きいことがわかりました。各実験区の付着膜の状態を比較した結果、付着物量(膜の厚さ)や付着膜に含まれる無機物量の違い、これらに起因した膜内への光の透過性(図2)や生藻類比の違いが、膜内の付着藻類の活性に影響を与えていると考えられます。
担当:皆川 朋子 |
 |
| ■写真−1 明暗瓶法による光合成速度の測定 |
|
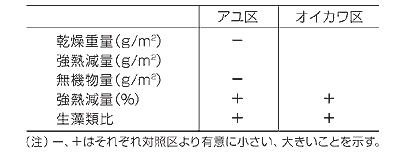 |
| ■表−1 摂食による変化 |
|
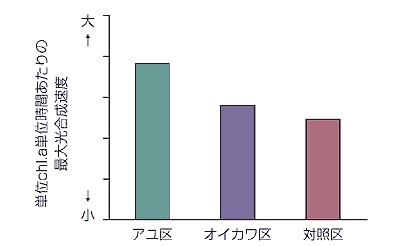 |
| ■図−1 最大光合成速度の比較 |
|
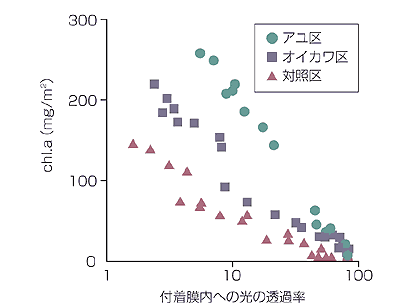 |
| ■図−2 光の透過率の違い |
 |
|