|
● 背景と目的
水際部には流心部と比較して流れの遅い場所が形成され、泳ぐ力の弱い小さな魚の生息場所となっています。たとえば、川に潜って注意深く観察すると、小さな魚が流れの遅い水際部に集まっているのを確認できます(写真1)。しかし、このような水際部の重要性は流心部の流れが速い場合と遅い場合では異なるのでしょうか?この疑問に答えるために、流心部の流れの速さを変えた時に、水際部に見立てた流れの遅い場所の利用割合が変化するかを実験的に調べました。
● 方法
実験には、水辺共生体験館の大型実験水路を利用しました。実験水路の片側の底に流れを弱める装置(鉄製のはしご状構造物)を設置し(図1)、その直上の流れが遅くなるようにしました。観察のために実験水路の横断面を上下左右3等分し合計9つの区画を用意しました。そのうえで、流心部の流れの速さを変化させ、放流した魚が流れの遅い区画の利用頻度を変化させるかを観察しました。実験対象魚には、実際の河川で一般的にみられるオイカワを用いました(写真2)。観察は、体サイズ(大・小)に分けて行いましたが、今回は観察例数が多かった小さいサイズの結果について紹介します。
● 結果と考察
流心部の流れの速さによって、オイカワによる利用区画は顕著に変化しました(図2)。流心部の流れが遅い時には、流れが最も遅いはしご状構造物の直上の区画をあまり利用しませんでした(図2上段)。一方、流心部の流れが速い時には、その流れが最も遅い区画を多く利用するようになりました(図2下段)。この利用区画の変化は、普段耐えられる流れの速さが体サイズの2〜3倍であるという一般則でよく説明できるので、流れの速い区画から遅い区画への避難の結果と考えられます。このように、流れの遅い場所は周りの流れが速い時に、より利用されたことから、水際部にできる流れの遅い場所の重要性も周りの流れによって変化すると考えられます。
今回の実験では、水路の流心部での流れの速さが21〜26cm/sの時に、流れの遅い場所が利用されました。野外の川の流心部では、これよりも流れの速い場所が多くみられます。このことから、流れの遅い場所を提供する水際部への配慮は多くの場所で必要であり、河岸の工事の際には特に注意が必要だと考えられます。
担当:小野田 幸生、佐川 志朗、上野 公彦、尾崎 正樹、久米 学、相川 隆生、森 照貴、萱場 祐一 |
 |
| ■写真1 水際で見られる小さな魚 |
|
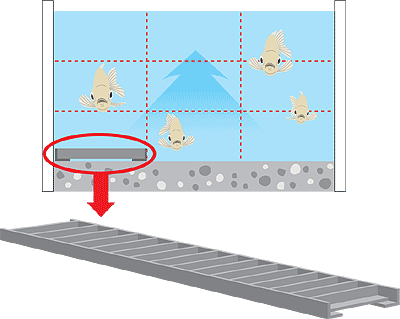 |
| ■図1 実験イメージ(上)と流れを弱める装置(下) |
|
 |
| ■写真2 実験対象のオイカワ |
|
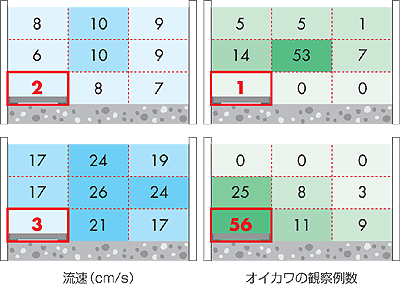 |
| ■図2 流れの速さの変化による魚の利用場所の変化 |
|
|