|
● 背景と目的
河岸は水域と陸域の遷移領域であり、河川風景や生物の生息場所として極めて重要な場所と考えられています。河岸を利用する生物のうち、非飛翔性生物は陸上を徘徊して移動するため、その場所の物理環境要因の影響を受けやすい生物です。過去の調査では、非飛翔性生物の生息密度と湿潤度・温度変動・緑被率との関係が認められています。しかしながら、それらの物理環境要因がどのように生物の定着に寄与しているかは解明されていません。そこで、これら3要因のうち湿潤度と温度変動を操作した野外実験を行い、河岸における湿潤度と温度変動の違いが非飛翔性生物の多様性にどのように寄与しているかを明らかにすることを目的としました。
● 方法
実験河川にコンクリート護岸を設置し、その表面に長方体のコンクリート部材を用いて横幅5m、縦幅3cm、深さ15cmの空隙を造成しました。その空隙に土壌を充填した後、散水装置による土壌湿潤度の調整と遮光ネットによる温度変動の調整を行い、全6調査区を設定しました(図1、2)。秋期に生物調査を行い、採集した生物のうち、非飛翔性生物(クモ目、ハチ目アリ科、コウチュウ目など)について、各調査区における多様度指数、分類群数(種数)、均等度を比較し、湿潤度と温度変動の違いが非飛翔性生物の多様性に与える影響を調べました。
● 結果と考察
湿潤度や温度変動の違いによって非飛翔性生物の多様度指数・分類群数・均等度に有意な差はみられませんでした(図3)。このことから、過去の結果も踏まえると非飛翔性生物の多様性は、湿潤度や温度変動ではなく、緑被率の影響を受けるものと考えられました(図4)。ただし、湿潤度は植物の生育に必要不可欠なため、非飛翔性生物の多様性に間接的に影響すると考えられます。また、湿潤度が高い場合には植物の生育を促すだけでなく、土壌の水分蒸発や植物の陰影により地表面の温度変動が抑制されます。過去の調査では、3つの要因が非飛翔性生物の多様性に及ぼす経路が不明確でしたが、本実験によって、これらの経路を推測することができました。以上より、河岸に生息する非飛翔性生物を保全するには、植物の生育が可能なレベルの湿潤度を護岸のり面に保持する必要があると考えられます。
担当:尾崎 正樹、相川 隆生、萱場 祐一、佐川 志朗 |
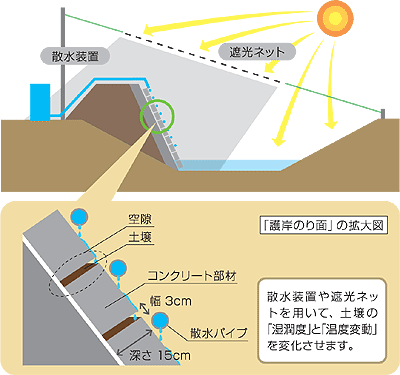 |
| ■図1 実験装置のイメージ図 |
|
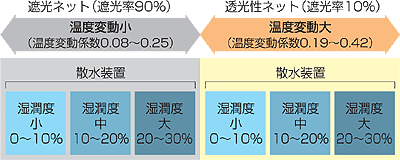 |
■図2 調査区の設定条件
(湿潤度は、土壌の堆積含水率の%を示す) |
|
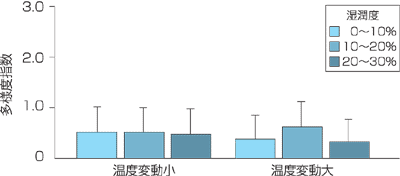 |
■図3 湿潤度と温度変動の違いによる多様度指数の平均値と標準偏差
(分類群数、均等度も同様の傾向を示したので、代表して多様度指数の結果を示す) |
 |
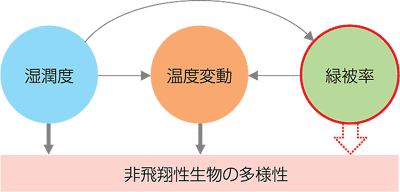 |
| ■図4 湿潤度、温度変動、緑被率と非飛翔性生物の多様性との関係についての推測 |
|
|